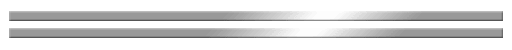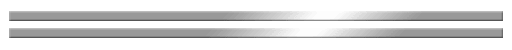土塁上に建つ天満社 |
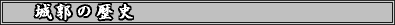
応永年間(1394年〜1428年)に、大友氏一族田原氏7代当主・田原親幸により築城された。
永享3年(1431年)親幸は大友氏の軍に従い、周防の大内氏との戦いに出陣して筑前で討死した。
天正8年(1580年)大友氏が耳川合戦で島津軍に大敗した直後、田原親貫は大友氏に叛旗を翻し国東で挙兵、麾下の水軍で府内の大友氏の本拠地を攻撃しようとしが、田原軍が国東を出発してから急に天候が悪化、海上は大時化となって親貫はやむなく引き返さざるを得なかった。
大友氏22代当主・大友義統は重臣を招集して田原親貫討伐を下知したが、重臣たちはこれに反対し、家臣の田北紹鉄が熊牟礼城で叛乱を起こした。
当時、大友宗麟は義統に家督を譲っていたが、この一大事にみずから出陣、速見郡日出町に本陣を置いて田原氏の安岐城・飯塚城、それに鞍懸城を攻撃した。
親貫は、毛利輝元・小早川隆景、それに筑前の秋月種実に援軍を依頼し、毛利軍は水軍を安岐浦に派遣したが、浦部水軍の若林鎮興らに撃退された。
安岐城でも激戦が展開され、宗麟の次男・親家は天正8年10月6日、これを攻め落とした。
大友義統は、八坂甚太郎に安岐城を預けたが、文禄2年(1593年)平壌城の戦いの失態で改易となり、大友領は豊臣家の蔵入地となった。
文禄3年(1594年)蔵入地の代官を任じられていた熊谷直盛は、安岐城と1万5千石を与えられたが、慶長4年(1599年)に目付として朝鮮征伐の遠征中に私曲ための行動があったと、同じ目付役の毛利吉成・竹中重利、さらには加藤清正・黒田長政らに訴えられ、五大老の裁定によって改易となった。
慶長5年(1600年)関ヶ原の合戦で西軍に属した直盛は、石田三成によって旧領・安岐を回復し大垣城に入り、安岐城は叔父・熊谷外記を城代として守らせたが、東軍に属する中津城の黒田孝高に野戦で敗れ落城した。
|
|